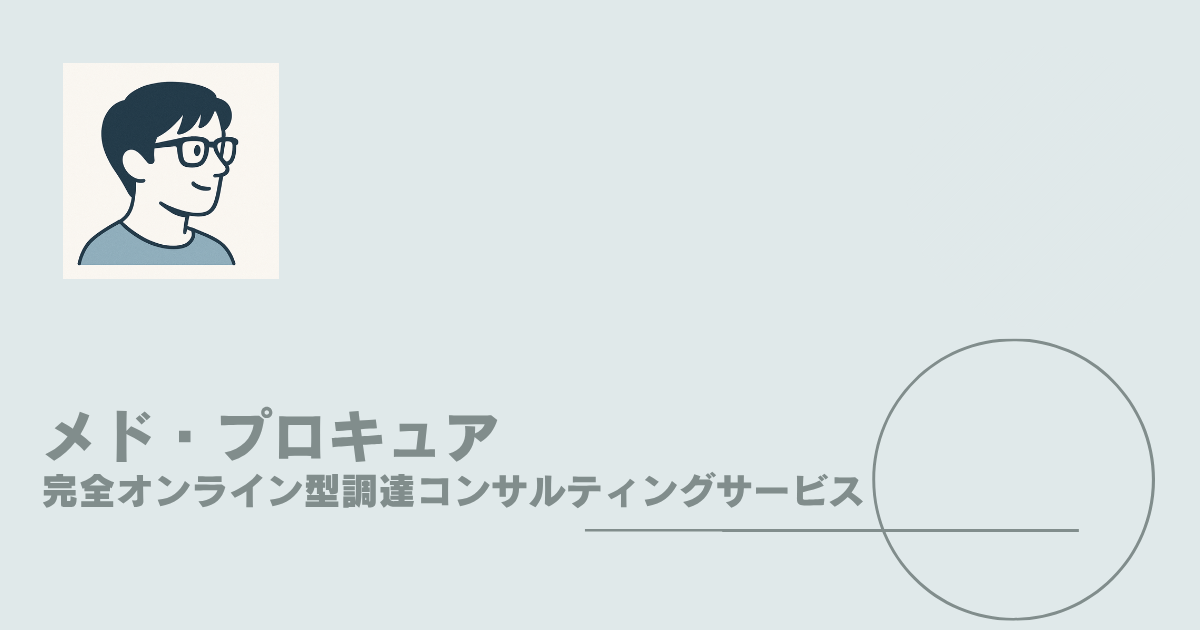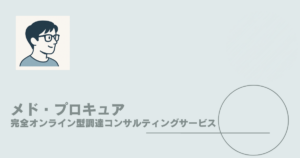「かかりつけ医が、ある日突然なくなる」──
そんな未来が、もはや他人事ではなくなってきました。
帝国データバンクが2025年7月に発表した調査によると、2025年上半期(1〜6月)に倒産した医療機関は35件にのぼり、前年同時期(34件)を超えて過去最多ペースとなっています。
この数字は、病院・診療所・歯科医院すべてを対象としたものであり、日本の医療インフラが構造的な転換点に差しかかっていることを示しています。
⸻
倒産の内訳と要因
まずは倒産件数の内訳を見てみましょう。
| 医療機関の種類 | 倒産件数 |
|---|---|
| 病院 | 9件 |
| 診療所 | 12件 |
| 歯科医院 | 14件 |
• 病院・歯科医院では過去最多水準。 • 負債10億円以上の大型倒産も4件(すべて病院)発生。 • 倒産の約97%が破産によるもので、北海道・東京・神奈川・奈良・兵庫・福岡など全国18都道府県に広がっています。
これらは一過性のトレンドではなく、複数の構造的要因が絡み合った“必然”の結果といえるでしょう。
⸻
収益悪化の連鎖──止まらぬコスト上昇、追いつかぬ診療報酬
今、医療機関を取り巻く最大の課題は、コストと報酬のバランスの崩壊です。
コスト面のプレッシャー
- 医療機器の価格高騰
- 看護師・技師など人件費の上昇(特に残業代負担)
- 給食費や電気・ガス・水道などインフラ費用の高騰
一方の収入は…?
- 診療報酬は「公定価格」のため、市場価格の変化に連動しない
- 2024年度診療報酬改定も実質的な増収効果は限定的
結果として、まじめに診療しても赤字という構図が固定化されつつあります。
⸻
経営者の高齢化と建物の老朽化──静かなる限界集落化
地方を中心に、中小規模の診療所や歯科医院では後継者不足が深刻です。
経営者自身が高齢であるうえ、事業承継に必要な資金や人材を確保できないケースが続出。
さらに、病院経営では老朽建物の問題が浮上しています。
2025年時点で1986年以前に設立された病院は全体の53.4%(帝国データバンク調査)
ところが、建築コストの高騰や資金調達難により、建て替えもままならず、設備面から倒産に追い込まれるケースも。
⸻
このままでは「年間70件超」も現実に──医療崩壊の入り口か?
現在のペースが続けば、2025年の医療機関倒産件数は初の70件台に達する可能性が高まっています。
診療報酬制度や公的補助が整備されているはずの医療業界で、なぜここまで経営破綻が広がっているのでしょうか?
一因として、医療機関の「公的機能」と「私的経営」のねじれが挙げられます。
公的役割を果たすためのコストは上がっているのに、報酬制度はそれに追いつかない。
結果、経営破綻を起こしても“潰せない”という矛盾した現実が医療現場を圧迫しているのです。
⸻
医療経営者に問われる「生き延びる選択」とは?
このような状況下で、医療経営者は単に“診療を続ける”だけでは生き残れません。
以下のような視点で、経営の再構築が求められています。
1. 採算管理の徹底と業務効率化
- 人件費の見直し(シフト管理・外部委託)
- 電子カルテや診療予約システムの最適化
2. 施設維持戦略の再設計
- リフォームか建て替えか、計画的な資金調達
- 既存施設の利活用(シェアクリニックなど)
3. 事業承継やM&Aの活用
- 地域内のネットワークでの統合・譲渡
- 民間ファンドや医療系VCとの連携
4. 行政支援制度の積極活用
- 病院建替補助、医療機器補助、事業承継助成
- 地域医療構想との連動による支援獲得
⸻
まとめ:医療経営は「戦略」が求められる時代に
今回のデータは、医療機関が「守られる存在」から、「戦略的に生き残る主体」へと変化を迫られていることを象徴しています。
- 経営の知恵
- 制度の理解
- 地域との連携
これらをバランスよく活用できるかどうかが、これからの医療機関経営の明暗を分けるでしょう。
ただ“いい医療を提供する”だけでは、医療機関はもはや存続できません。
経営と現場、その両輪で走るためのアップデートが今、必要です。
調達でモヤモヤしていたら、
まずは、聞いてみてください。
医療ITや機器の導入で「これでいいのか?」と感じたら、
匿名でも大丈夫。トウカンが中立の立場からお手伝いします。