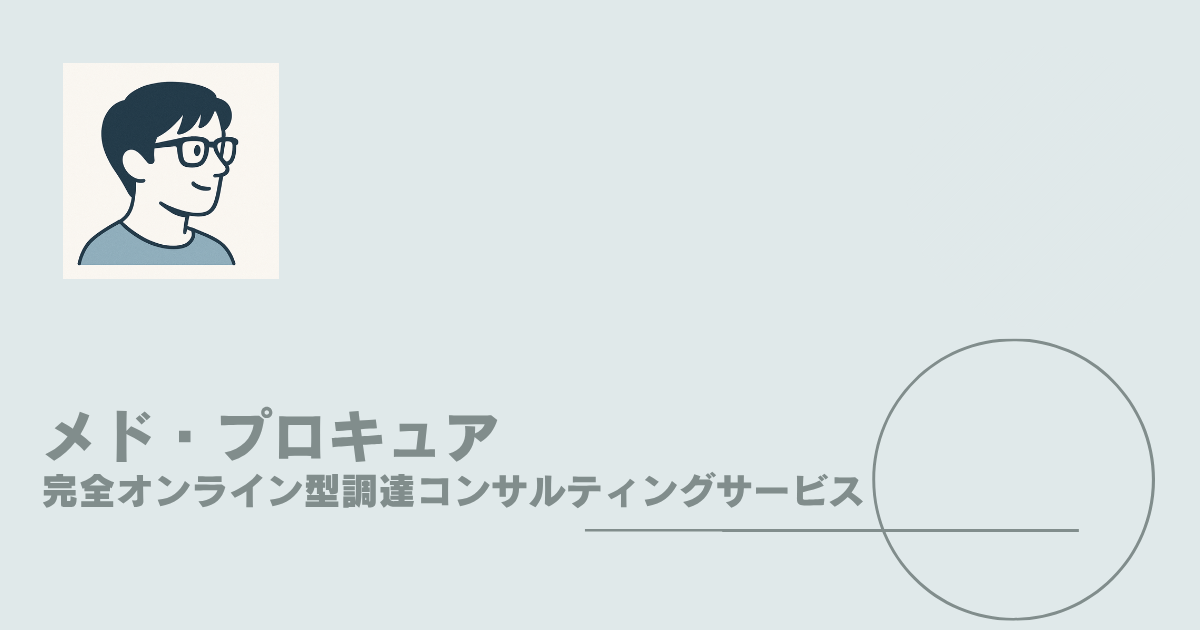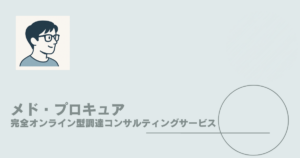医療機器の導入には、医療機関側とメーカー・ディーラー側での「ズレ」がつきものです。
- 医師が望む機能と、営業が売りたい機器
- 医療の質向上と、経営上の回収可能性
- 感覚的な「欲しい」と、数字で裏打ちされた「必要性」
本記事では、医療機器メーカーの営業構造・医療ディーラーの現実・医療機関側の判断軸・そして冷静な費用対効果に至るまで、調達現場のリアルを解き明かします。
⸻
1. 医療機器メーカーの思惑|営業現場には2つのパターンがある
A. 社内決裁重視型(老舗・大手メーカー)
- 割引や特注対応に限界がある
- 社内決裁が通ることが最優先
- 「売れるか」より「承認されるか」が営業判断
B. 実績拡大フェーズ型(新興・成長企業)
- 価格や条件で勝負する柔軟性あり
- 初期導入を優先し、価格を崩してでも攻める
- KOL獲得や症例数増加が社内評価指標
👉 医療機関側がこの「営業のフェーズ」を読み解くことが、交渉の主導権を握る鍵になります。
⸻
 サイト運営者<br>トウカン
サイト運営者<br>トウカンメーカー・機器のポジショニング。そして、本当に売りたいのか?を確認
2. 医療ディーラーの“売りたい”と“売れる”の裏事情
医療ディーラーは中立と思われがちですが、次のような現実があります:
- 利益率の高い製品を優先:メーカーからの販売奨励金がある
- 在庫処分対象製品の提案:倉庫事情が関係してくる
- トラブルが少ない機器を推す:アフター対応負担を避けたい
👉 結果、「医師が本当に欲しい機器」が最初の提案から外れていることも少なくありません。
⸻



ディーラーが、売りたい機器・メーカーがあることを知ろう
3. 医療機関の導入理由は一枚岩ではない
医療機関が導入を検討する理由は、主に以下の3パターンに分類されます:
導入理由 内容
故障によるリプレース 最優先は「納期」と「即稼働」。価格よりスピード
計画更新(耐用年数終了) 同型機種の後継で十分。冒険は避けがち
増設・新規開業 標準化か価格重視かの分岐点。複数メーカー比較が発生
👉 その導入理由ごとに、求める提案やスペックは全く異なります。
⸻
4. 見積もりの“妥当性”は誰が検証するのか?
メーカー提案、ディーラー提案、そして営業トーク。
情報量が多くなる中で、見積書の「正しさ」や「比較の軸」が不明確なまま、決裁されていく例も少なくありません。
そこで必要なのが、“中立的な目線”による調達のセカンドオピニオンです。
- 現場の使い勝手と価格のバランス
- 保守契約の妥当性と将来負担
- 「比較表」ではわからない真の違い
⸻



比較資料は必ず作成しましょう
5. 「どうしても欲しい」気持ちと、冷静な費用対効果の再点検
医療機器を導入する際、現場の医師や技師が「どうしてもこのメーカーのこの機能が欲しい」と強く希望するケースは少なくありません。
たとえば:
- 高解像度のOCT(眼科用断層撮影装置)
- AI補正付きの画像診断装置
- 特定の企業のUIが好み
これらの“こだわり”は、時に医療の質の向上や患者満足度につながる重要な判断ですが、一歩引いて見ると、医療報酬体系上の収益構造と、機器コストのバランスという視点が抜けがちです。
⸻



決裁権者が、冷静に判断できる環境・データを用意しよう
医療機器にかかる費用は変動するが、診療報酬は固定
- 例えば、A社の装置は800万円、B社の装置は500万円
- しかし、保険点数で得られる収入は同一
つまり、高額な機器を導入しても、収益が増えるわけではないケースが大半です。
⸻
同時に、ブランドや使い勝手に対する信仰は今もまだあります。
ルイヴィトンやエルメス、ソニーやパナソニックのように、慣れ親しんだメーカーや確固たるポジショニングがある装置もまだまだあります。
例えば、オリンパスの内視鏡。ライバル企業がAI等々の最新機能で肉薄するも、揺るがない優位性も存在します。
このような場合、本命のオリンパスを少しでも良い条件で購入するのか。
条件が合わなければ、他社も積極的に評価をするのか。
この点に関しては、同じ施設内の人間だけでは判断に迷う時もあるはずです。
欲しい機能は「本当に使うのか?」
• 付加機能(自動測定・クラウド連携・AI補正など)は便利 • しかし「どれだけの頻度で活用されるのか?」という問いは盲点になりがち • 導入後に「宝の持ち腐れ」となるケースも少なくない
⸻



目玉の機能は、後から後悔する話もよく聞きます
「好きな機器」と「最適な投資」は違う
医療機器導入には、以下の2つの視点が必要です:
視点 内容
この両者のバランスをどう取るかが、医療機関の経営判断として極めて重要です。
⸻
小さなクリニックほど冷静な“費用対効果”視点が重要
中小の医療機関やクリニックでは、1台の医療機器投資が経営に与える影響は極めて大きいものです。
診療の質を担保しつつも、過剰投資を防ぐ判断は、単なる価格交渉以上に高度なバランス感覚が求められます。
このとき第三者的な「評価」や「導入助言」があると、感情的な判断だけに偏らず、より実務的・経営的な結論が導き出せます。
⸻
6. 「誰がために導入するのか?」を問い直す
最終的に重要なのは、その導入が「現場」と「経営」の双方にとって納得感があるかです。
| 比較軸 | 医療機器メーカー | 医療ディーラー | 医療機関(現場・経営) |
|---|---|---|---|
| 優先事項 | 売上・実績・承認通過 | 販売奨励・利益率 | 稼働性・収益性・保守性 |
| 判断基準 | 営業計画・社内承認 | 在庫・取引都合 | 実運用・費用対効果 |
このギャップを埋めるには、「中立的な第三者」の介入がますます求められているのです。
⸻
まとめ|その導入判断に、透明性と納得感はあるか?
医療機器の導入は、単なる価格交渉やカタログ比較では済まされません。
• 「なぜその機器を選ぶのか?」
• 「機能と価格のバランスは取れているか?」
• 「その投資は、どのくらいの期間で回収できるのか?」
⸻
▶ 調達に迷ったら、「セカンドオピニオン」という選択を。
現場と経営、両方の視点に立った中立的なサポートで、納得の調達を実現しませんか?
調達でモヤモヤしていたら、
まずは、聞いてみてください。
医療ITや機器の導入で「これでいいのか?」と感じたら、
匿名でも大丈夫。トウカンが中立の立場からお手伝いします。