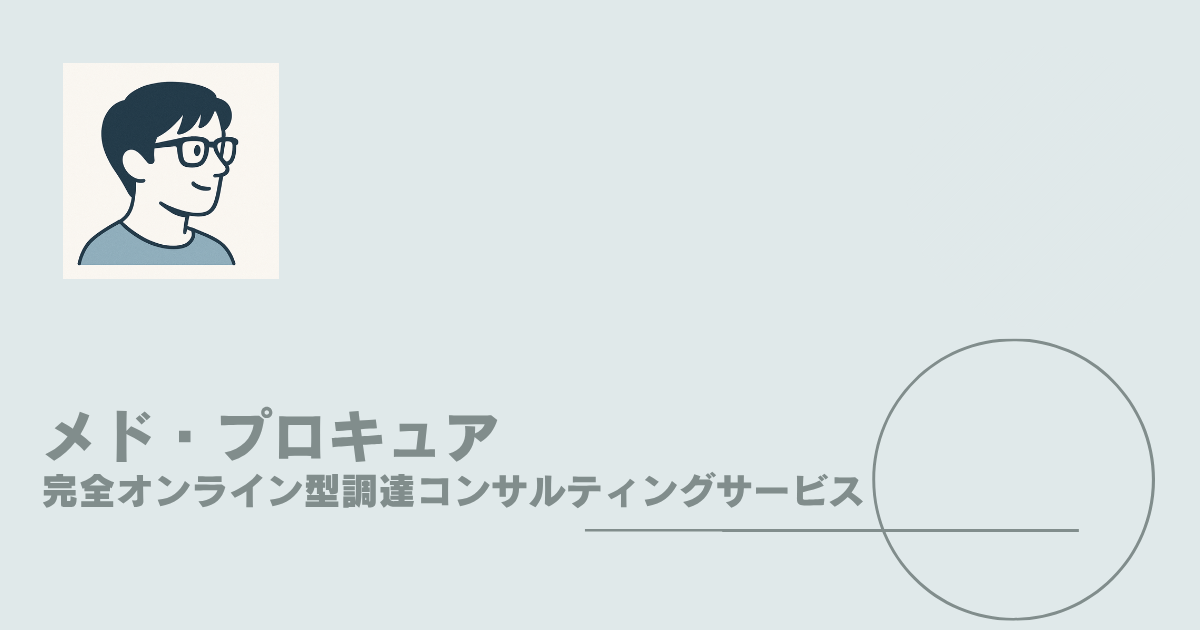医療機関において、調達という行為は”治療”と同じく、非常に重要な判断の積み重ねです。
機器、システム、サービスを選ぶことは、医療の質やスタッフの働きやすさ、そして経営の健全性に直結します。
しかし、その大切な場面において、意外なほど多くの医療機関が「ひとつの見積書」だけを頼りに意思決定をしてしまっています。
今回は、そのような状況に対して私(トウカン)が提供している「中立的な調達支援」という考え方について、背景と必要性、そしてどのような場面で役立つのかをご紹介します。
■ 医療調達は、なぜ孤独なのか?
医師や院長が「導入したい」と思う製品を探すとき、多くは以下のルートで情報を得ます:
- 展示会や学会で話を聞く
- 医療業界の知人から紹介される
- ベンダーから直接提案される
ところが、この段階ですでに“選択肢”がかなり絞られてしまっているケースが多くあります。
製品の性能比較や価格の妥当性、そもそもその構成が自院に最適かどうか──これらをフラットに検証できる場が、現実には非常に限られているのです。
特に中小の医療機関やクリニックの場合、内部にITや機器選定に詳しい人材が常駐していないことも多く、院長やごく少数のスタッフが調達判断を担う構造になっています。
時間も限られ、相談できる相手もいない中で、重たい意思決定をひとりで背負っている現場が非常に多いのが実情です。
■ 「相見積もりを取ったから安心」ではない理由
「うちは3社から相見積もりを取ってるから大丈夫です」
よく聞く言葉ですが、実際にはこの“相見積もり”自体が機能していないケースも少なくありません。
- 比較対象の前提条件がそろっていない(スペックが微妙に異なる)
- 各社が見積もる構成がバラバラ
- 曖昧なヒアリング内容に基づいた提案
これでは価格の「高い・安い」以前に、比較の軸がブレてしまい、正しく判断することができません。
しかも、各社の営業担当は自社の製品やサービスを売るために動いており、当然ながら“第三者としての助言”をしてくれるわけではありません。
さらに、出入りの業者に相談しても「売る立場」にある以上、そのアドバイスが本当に中立とは限らないという問題もあります。院長が信頼しているつもりでも、その業者がすべての選択肢を提示しているとは限りません。
一方で、大手の医療系コンサルティング会社に相談しようとすると、最低でも数十万円単位の費用が発生し、クリニック単位の意思決定にはオーバースペックであったり、予算的に現実味がないという声も多く聞かれます。
 サイト運営者<br>トウカン
サイト運営者<br>トウカンもちろん、医師が買いたいモノがある時は別のアプローチになります
■ 中立的支援がもたらすもの
私(トウカン)は、医療機器やITの導入において“売る立場”と“買う立場”の両方を経験してきました。その経験を活かし、クライアントにとって以下のような支援を提供します:
- 複数の見積もりを「仕様ベース」で正確に比較
- ベンダーごとの得意・不得意分野を補足
- 提案内容の“過不足”を指摘(多すぎない/足りていない)
- 実際の導入後の運用も見越した構成案を再検討
つまり、意思決定の「地ならし」となる情報をフラットに整える役割を果たします。
■ 第三者の目線は恥ずかしいことではない
医療において、治療方針に悩んだ患者さんが他の医師の意見を求めることは、もはや常識です。
それと同じように、調達という重要な局面で第三者の視点を取り入れることは、より良い選択をするための前向きな行動です。
特に、数十万〜数百万円規模の調達であれば、数%の価格差や、機能の差がその後の運用に大きく影響します。
にもかかわらず「時間がない」「誰に聞けばいいかわからない」「ベンダーに悪い気がして言いづらい」などの理由で、その機会を失ってしまっている現場が多すぎるのです。



納得感って実は難しいかも
■ 最後に:ひとりで抱えない、という選択肢
私たちは、「提案書や見積書をじっと眺めながら、なんとなく不安を抱えている」そんな方のために存在しています。
「ちょっと聞いてみるだけ」でも構いません。
匿名でも、事前に資料がなくても、最初の一歩はとても軽くていいのです。
医療調達の判断に、中立的な視点を──それは、選択の質を上げるためのもうひとつの“知恵”です。
🗂 ご相談はいつでもどうぞ
調達でモヤモヤしていたら、
まずは、聞いてみてください。
医療ITや機器の導入で「これでいいのか?」と感じたら、
匿名でも大丈夫。トウカンが中立の立場からお手伝いします。
サイト運営者:トウカン
医療調達のセカンドオピニオン。“なんとなく高い”を見える化する存在。