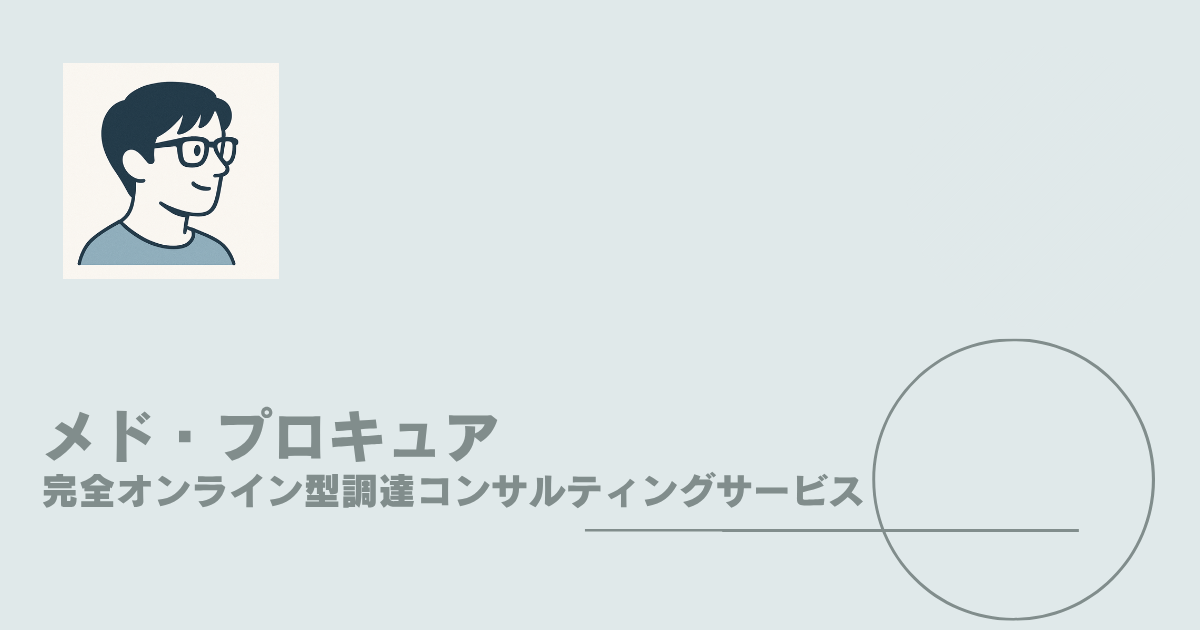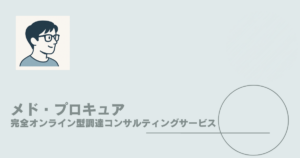近年、国を挙げて推進されている医療DX。その中核を担うのが「標準型電子カルテの共通化」です。
全国の医療機関が同じ仕組みで電子カルテを使い、患者情報をシームレスに共有できる体制を整えるという構想です。
しかし、現場では**“費用の高騰”と“現場の反発”**が深刻な問題になっています。
 サイト運営者<br>トウカン
サイト運営者<br>トウカン実際に、同一ベンダーのリプレースで2割以上更新費用が上がっているとの情報もあります
現場で起きている2つの現実
① 想定をはるかに上回る導入コスト
2025年6月、日経新聞が報じた事例では、ある自治体病院で当初11億円と見積もられていた導入費用が、実際には28億円にまで膨らんだことが明らかにされました。
これは一例ではなく、各地の病院で同様の事態が起きています。
💬 自治体職員の声:
「これだけ予算が膨らむなら、他の事業を止めるしかない」
「既存のシステムで問題なく運用していたのに、なぜこの仕様が必要なのか分からない」
② 医師・現場スタッフの“反発”と“困惑”
2024年4月、日経メディカルが現場の医師たちの声を紹介しています。そこには次のような生の声がありました:
- 「既存の電子カルテが十分に機能しており、わざわざ変える理由がない」
- 「標準仕様に合わせるために必要な業務フローの変更が多すぎて非効率」
- 「一部の機能が現場のニーズにまったく合っていない」
特に地方の自治体病院では、「現場を知らない中央主導の導入」が、“混乱と不信”を生んでいるのが実情です。



そのまま、使い続けるだけでいいのに という気持ちですね
>病院情報システム(5年リース)の費用構成は、一般的に「モノ4割、ヒト6割」である
— 診療情報管理士のノブ(フェイク) (@HIMnobu) March 23, 2025
一般的にとか言っちゃってるし、そもそもこの試算ガバガバ過ぎません???
国立大学病院長会議 電子カルテシステムの価格高騰を問題視 診療報酬での対応など国の支援求める https://t.co/nM5qHtiMDc pic.twitter.com/0CKlp96Uvo
高騰・混乱を引き起こす3つの構造的問題


1. ベンダーが実質的に固定化されている
調達は競争入札の形式を取っていても、電子カルテの共通仕様に対応できるベンダーは限られており、価格交渉力が自治体側にない。
2. 要件定義が曖昧なまま「標準化」が先行
現場の業務フローや診療科の特色を無視した共通仕様により、「現場が仕様に合わせる」設計になってしまっている。
3. 技術的助言を得る体制が不足
多くの自治体には、電子カルテに関する技術的中立アドバイザーが不在で、価格の妥当性や仕様の正当性を検証できず、ベンダー主導の提案がそのまま通る構造がある。
今こそ必要な「調達のセカンドオピニオン」
専門コンサルは高コスト。だからこそ「育成」と「スポット支援」の併用を
電子カルテの導入・更新に際して、「中立的な第三者の関与が必要」といっても、実際に外部コンサルタントを本格導入することは簡単ではありません。
特に自治体病院においては、以下のような現実的な壁があります:
- 💰 システム本体が高額なうえに、コンサル費用まで加わると財政的に耐えられない
- 🧑🏫 社内に知見が乏しく、ベンダー任せの構図から脱却できない
- ⌛ 内部人材を育てたいが、育成には時間も経験もかかる
このような背景から、現場では“コンサルを入れられないから全部ベンダーに頼る”という構造が温存され続けています。
しかし、これでは根本的な課題は解決できません。



コンサルを入れても、価格的に割に合わないかもしれない
解決策:必要な時だけ活用できる「スポット型コンサルティング」
そこで提案したいのが、“必要な時に、必要な内容だけ”を問い合わせられるスポット型のコンサルティングです。
🔍 たとえば、こんな使い方が可能です
| シーン | スポット相談の活用例 |
|---|---|
| 要件定義の前段階 | 仕様書の方向性や現場業務との整合性チェック |
| ベンダー選定時 | 複数見積の比較評価・価格の妥当性レビュー |
| 導入スケジュール策定時 | 無理のない移行計画へのアドバイス |
| 導入後のトラブル発生時 | 中立的な第三者評価・再調整支援 |
こうした**「ピンポイントでの中立的助言」**を得ることで、自治体側はコンサル費用を抑えながらも、過剰投資や失敗導入のリスクを軽減することができます。



ここのフェーズで、外部の力の要不要があります
病院組織の情報リテラシーを“底上げ”する仕組みづくりを
中長期的には、自治体や病院内で電子カルテや情報システムに関する最低限のリテラシーを持った担当者の育成が不可欠です。
ただし、それには年単位の時間と実践が必要。
だからこそ、**「自走」と「外部知見の活用」**を上手く組み合わせることが、これからの調達戦略の鍵になるといえます。
✔ 本当にその仕様が必要か?
標準化に振り回されていないか?
「現場に合った仕様」か「共通化のための仕様」かを見極める必要があります。
✔ 本当にその価格は妥当か?
他施設と比較して高すぎないか?
一社だけの見積もりに頼らず、価格構造の妥当性を可視化することが必要です。
✔ 本当にその導入は価値があるか?
“導入のための導入”になっていないか?
患者の安心や医療の質に本当に資するかを再評価すべきです。
自治体・医療機関に向けた提言
| 対応項目 | 内容 |
|---|---|
| ✅ 技術的アドバイザーの外部活用 | 中立的なコンサルや技術パートナーを導入初期から関与させる |
| ✅ 要件整理の主導権を自治体側に | ベンダー任せにせず、現場と一体となった要件定義を実施 |
| ✅ 入札設計の見直し | 一社独占にならないような仕様設計と公開性の確保 |
| ✅ 移行コスト・運用コストの見える化 | 初期導入費用だけでなく、5~10年単位でのTCOを試算 |



本当に必要なサポートを選びたいですね
最後に:その見積もり、「本当に妥当」ですか?
電子カルテ導入は、単なる“IT投資”ではありません。
それは地域医療の未来と、自治体財政の両方を左右する経営判断です。
私たち「メド・プロキュア」は、ベンダーでも自治体でもない**“中立的な第三者”としての調達支援**を提供しています。
「その仕様、妥当ですか?」
「その見積もり、納得できますか?」
迷いや不安を感じたとき、もう一つの視点=セカンドオピニオンをご活用ください。
※この記事は、「日本経済新聞」(2025年6月16日)および「日経メディカル」(2024年4月)の公開情報をもとに構成しています。
調達でモヤモヤしていたら、
まずは、聞いてみてください。
医療ITや機器の導入で「これでいいのか?」と感じたら、
匿名でも大丈夫。トウカンが中立の立場からお手伝いします。
サイト運営者:トウカン
医療調達のセカンドオピニオン。“なんとなく高い”を見える化する存在。